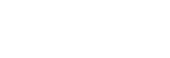FEATURE
- CROSS TALK #02
-
- 「最高にクリエイティブ」
- サービスマンという仕事
-
- 山下 哲也氏
- カフェ・ド・フロール
ギャルソン
1885年に創業したパリのカフェ・ド・フロールは多くの文化人に愛されてきた。このカフェで働くギャルソンは、伝統的に白人のフランス人のみ。その不可能を可能に変えた唯一の外国人ギャルソンが山下哲也さんだ。
1肩書ではなく「人」として勝負する仕事がしたかった
─ なぜギャルソンという仕事を選んだのですか?
山下大学時代に表参道のカフェ・ド・フロールでアルバイトをしていた時、京都の店の立ち上げに行ってほしいと言われました。その中にパリから来たミッシェルというギャルソンがいて、日本語も話せないのにお客さんとコミュニケーションを取るのが上手いんですね。人間力があるというか。その時にこういう人間になりたいと思ったんです。
それは、大学4年生でちょうど就職活動に行き詰っていた時期でした。言葉とか、スキルとか、知識とか、肩書ではなく、ひとりの人間として裸一貫で勝負する、こんな仕事がしたいとその時に思ったのです。
- ※「ギャルソン」は主にフランス料理のレストランやカフェなどで使われる用語で、サービスを担当する男性のことを指す。カフェ・ド・フロールのような老舗のギャルソンは、世界の超一流の人々を顧客に持ち、料理人と同じように技能職として尊敬を集めている。とくにカフェのギャルソンはフランス独特の職業であり、山下さんは「フランス文化の継承者」と説明する。

- 山下哲也
ギャルソン
世界で最も由緒ある老舗カフェ、パリ6区サンジェルマン=デ=プレの、カフェ・ド・フロールのギャルソン。2007年には、Newsweek誌において、世界が尊敬する日本人100人に選ばれた。2002年渡仏。2003年夏より外国人で初めて、世界で最も由緒ある老舗カフェのギャルソンとして立つ。現在、世界の名だたる著名人を含む、多くの常連客から指名を受けるギャルソンとして活躍する。
─ 他の仕事は考えなかったのでしょうか?
山下それまでは商社マンになりたいと思っていました。
僕の家はすごく固くて、一流企業や官僚の親戚ばかりなのですが、たまたま商社に勤めている人がいなかったのでそこを狙うつもりでした(笑)。ある意味、カフェのギャルソンも、誰もやっていないというところに惹かれた部分はあります。
最終的に、この仕事を極めるためにはパリに行くしかないと思っていました。
“世界の首都”パリを舞台に勝負してみたいという欲望を抑えきれなくなってしまったのです。パリでギャルソンになることが目的ではなくて、そこで何ができるかを自分の目で見てみたかったのです。
もちろん、その選択肢は家族からものすごく反対されましたよ(笑)。
パリに行く時は、「1年間時間を下さい。これでだめだったら違うことやります」と頼み込んだんです。
─ ギャルソンを一生続けられるのか、という不安はなかったですか?
山下それはなかったです。あったらパリに行ってないですね。
『カフェ・ド・フロールのギャルソンは、白人のフランス人のみ』という不文律があります。移民国家という側面をもつフランスの中でもかなり特殊で排他主義を貫くものですが、それはパリの象徴であるカフェ・ド・フロールというイメージを守るためです。
2002年に渡仏してパリの語学学校に通いながら、ただ待つしかなかったんです。
総支配人からはもうちょっと待ってくれと言われ続けていましたが、もちろんなんの保証もなかった。でもヘンな自信だけはありましたね。
僕はそれを“意志を孕んだ予感”と呼んでいます。これは僕の好きな村上龍さんの小説に出てくる言葉なのですが当時の僕の心境にぴったりでした。
─ ギャルソンという仕事をどういうふうにとらえていますか?
山下サービスの仕事は愉しい面もありますが、ある意味でとても厳しい、シビアな世界だと思います。自分とお客様という、人対人の勝負です。一言でいえばお客様に“惚れさせてなんぼ”の世界です。
昔ながらの歩合制のシステムで給仕をつとめるカフェのギャルソンは尚更です。それは、シンプルで美しく、そして残酷な世界です。各々の給仕人が自分が受け持つテーブルで己の才覚だけで勝負する、こんなにやりがいのある仕事って他にはないでしょう!(笑)
例えば料理人はお皿をひとつクリエイトします。そして、その料理を求めてお客様はリピートしますが、サービスマンの場合は、自分の存在ひとつでお客様にリピートしてもらえるかどうかが求められます。だから厳しいけれどすごくクリエイティブな仕事でもあるといえる。また、お店のスタイルに則した一般的なオペレーションのマニュアルはあるけれど、その中で自分なりのアプローチはいくらでもできるからです。
サービスの仕事を始めると最初は新鮮で楽しいかもしれませんが、それがルーティンワークになってしまうとなんにも面白くないんです。サービス・接客という仕事は完成することがないので、一生修行みたいなもの。だけど職人のように何かを形に残すこともないし、評価の規準もありません。だから、だいたいはその先の愉しさを味わえないうちに挫折しちゃったり、やめてしまったりするんですよね。それはもったいないですね。愉しさは、その先にあるのですから。